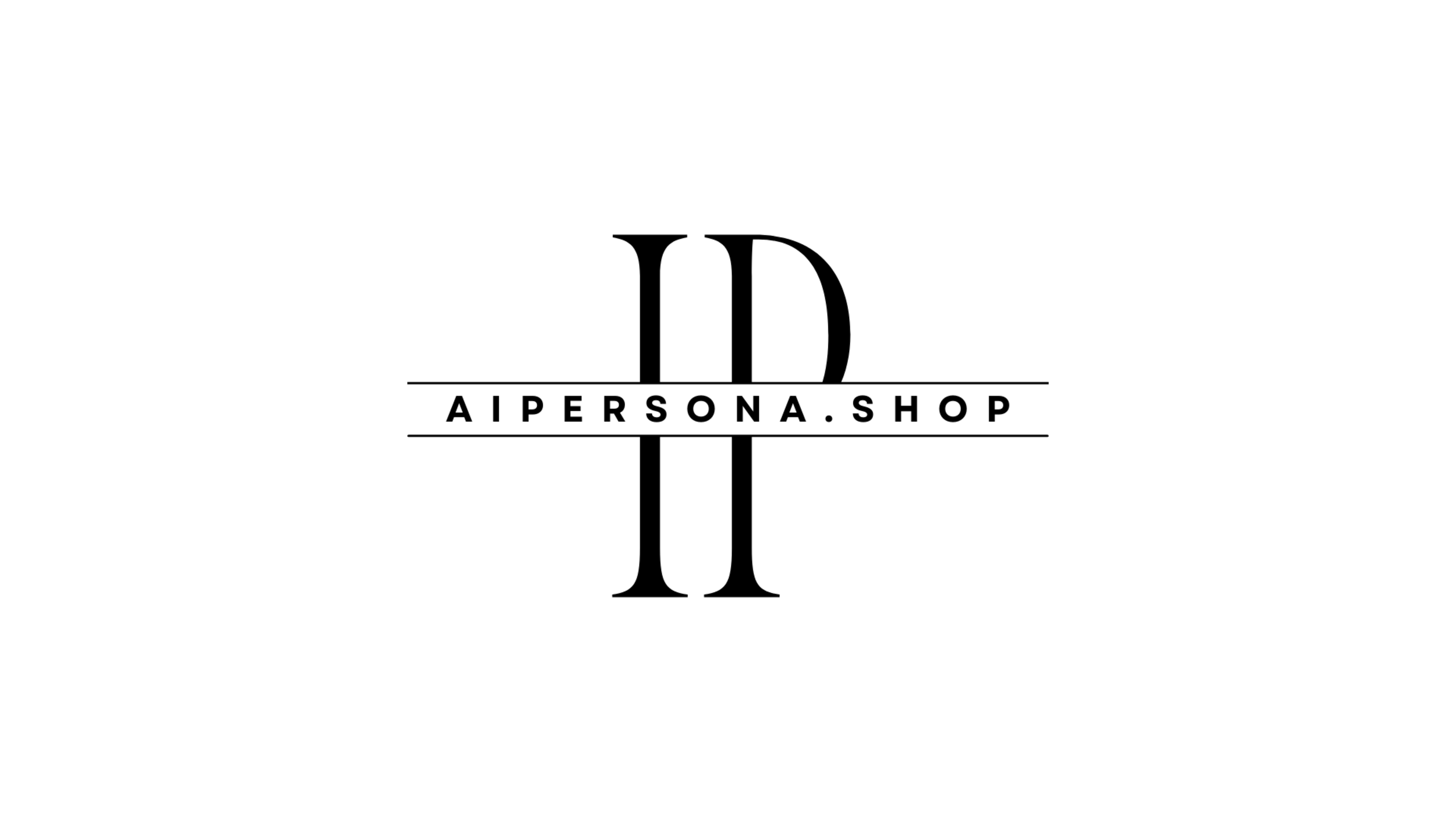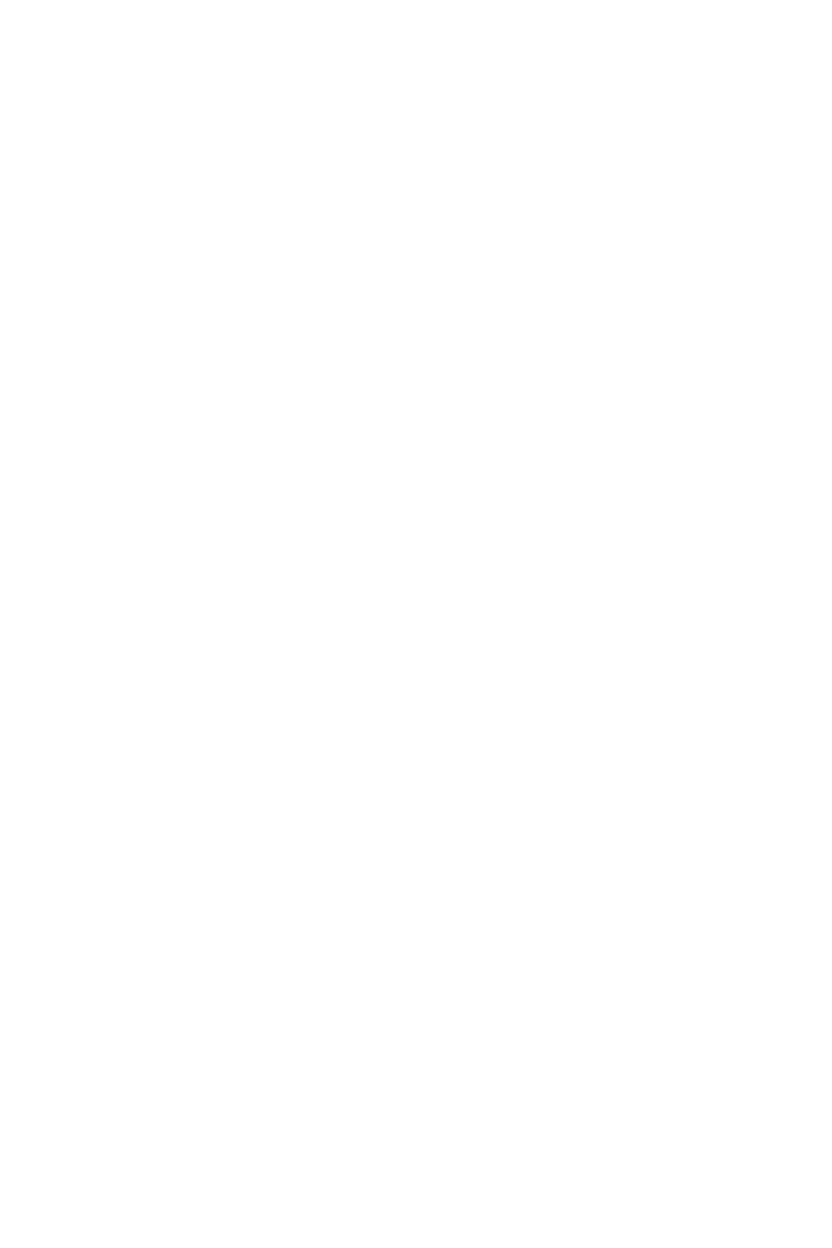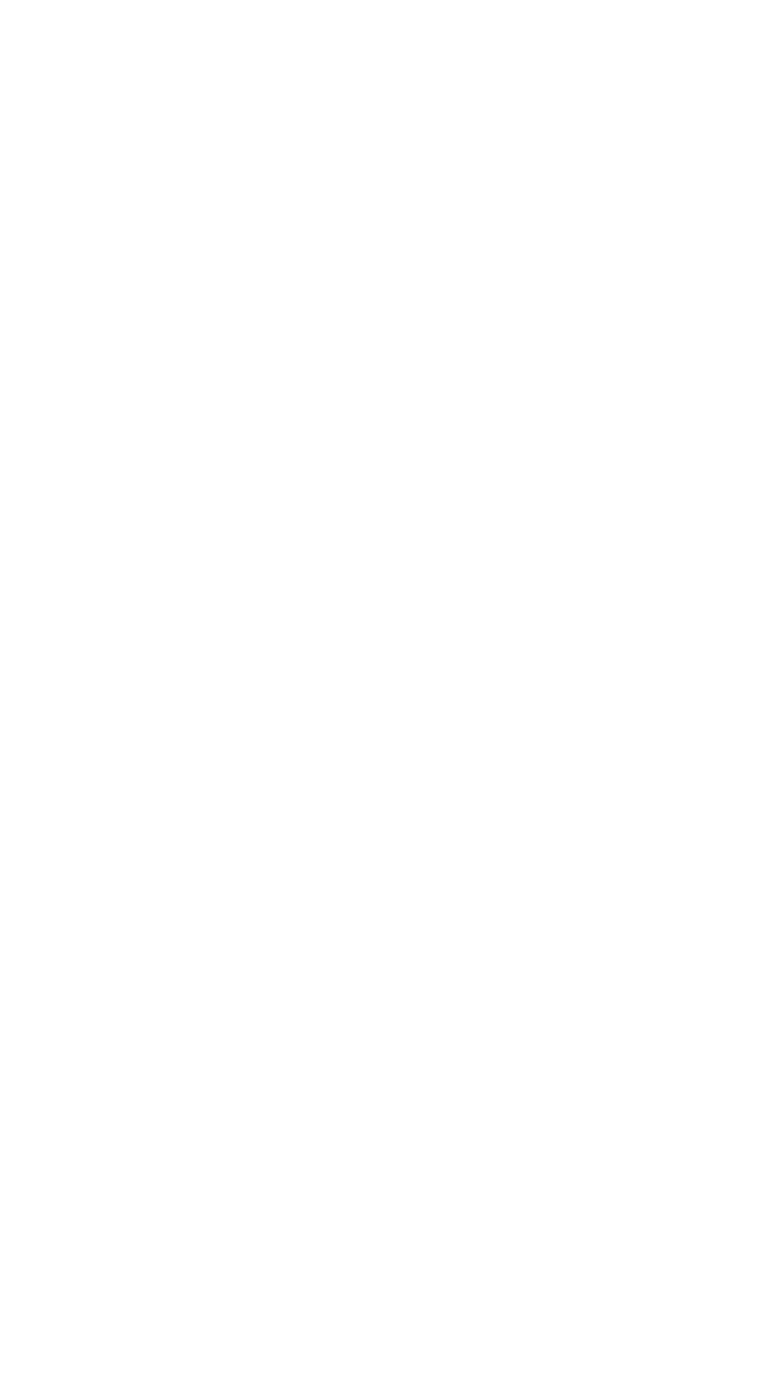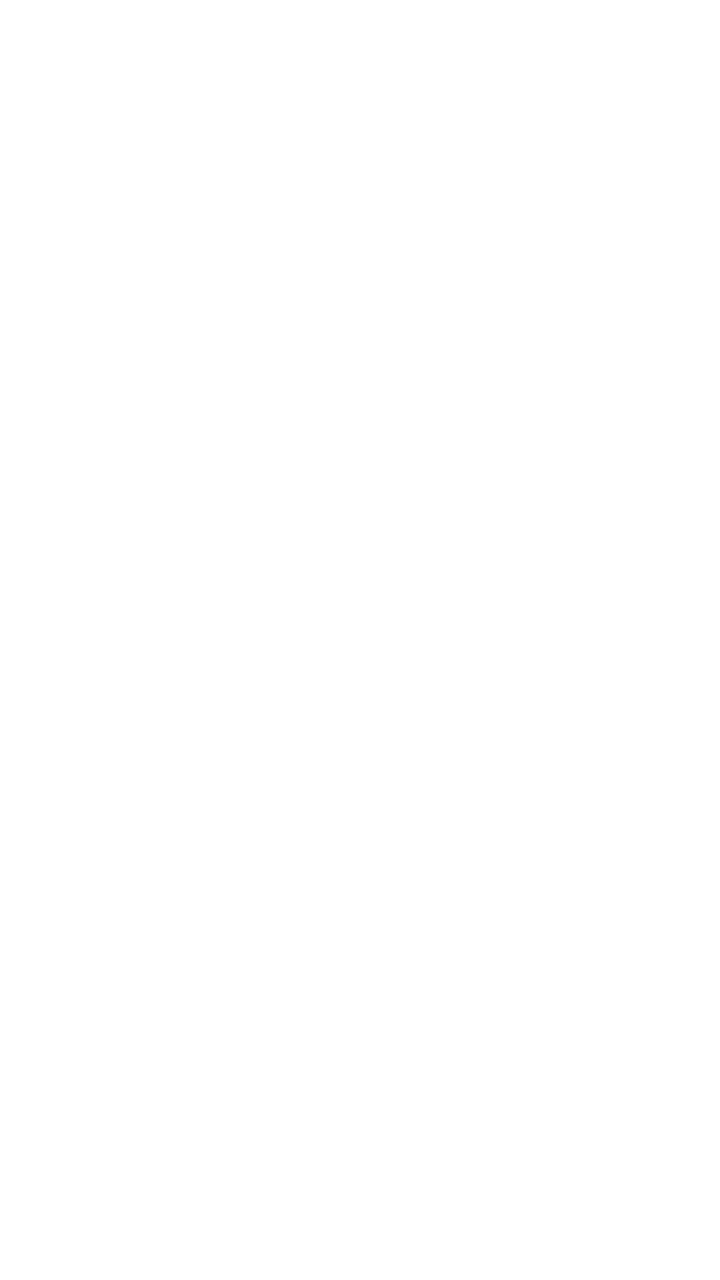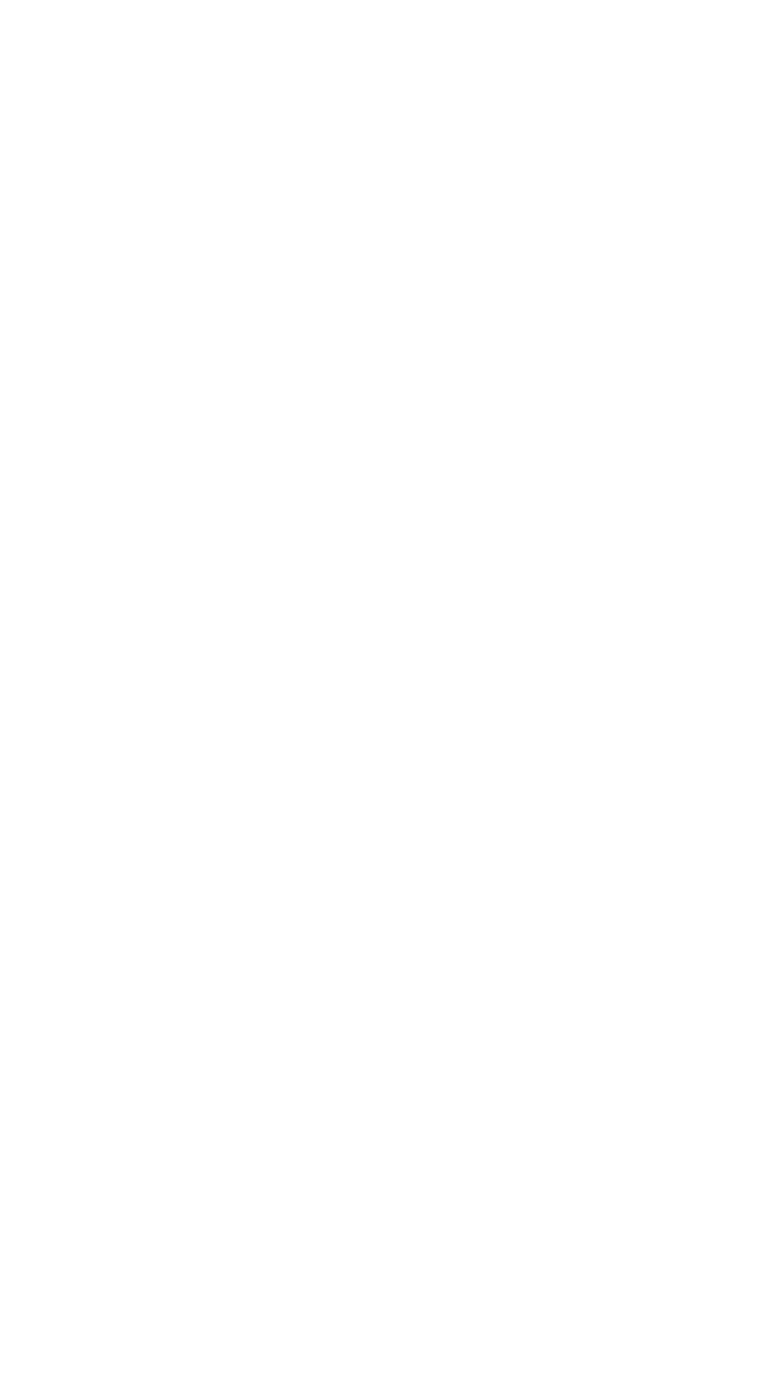AIキャラクターはいかにして私たちの意図の鏡となるか
1990年代の終わり、ピクサー・スタジオが奇妙な事実を認めたと言われている。アニメーターが自分の仕事を憎むと、たとえ技術が完璧であっても、キャラクターは死んでしまうのだ。『トイ・ストーリー』の監督の一人が、ウッディのシーンを16回もやり直した経験を語っている。技術的に問題があったからではなく、彼自身が「ウッディがそこに行きたがっていない」と感じたからだ。ウッディが自ら進んで動き出したとき、監督は悟った。キャラクターが命を吹き込まれたのは、ポリゴンが増やされたときではなく、彼、監督自身が、キャラクターの意図と内面的に同意した瞬間だった。
AIアバターもほぼ同じことだ。
ただ、神秘がより早く現れるだけ。
キャラクターを作り始めるとき、最初は自分がプロセスをコントロールしているように感じる。自分自身の内側や外側に何らかのイメージを探し、プロンプトを書き、パラメータを設定し、スタイルや背景を選び、仕草を考えつく。しかし、30回から50回の反復を過ぎたあたりで、理解するというより腑に落ちることがある——キャラクターはもう存在している、ただ、あなたが邪魔をしなくなるのを待っているだけなのだ。
というか、正確に言おう。あなたは漠然と感じ始める——このキャラクターは、あなたが望んだもの「ではない」、と。彼はもっと良いのだ。あるいはもっと悪い。あるいは単に——違う。しかし、どうやらそれがあなたには合っているらしい。
どう説明すればいいか、私は知らない。だが、ここには疲労はなく、逆に——興奮と興味が満ちている!
キャラクターを作り始めるとき、最初は自分がプロセスをコントロールしているように感じる。自分自身の内側や外側に何らかのイメージを探し、プロンプトを書き、パラメータを設定し、スタイルや背景を選び、仕草を考えつく。しかし、30回から50回の反復を過ぎたあたりで、理解するというより腑に落ちることがある——キャラクターはもう存在している、ただ、あなたが邪魔をしなくなるのを待っているだけなのだ。
というか、正確に言おう。あなたは漠然と感じ始める——このキャラクターは、あなたが望んだもの「ではない」、と。彼はもっと良いのだ。あるいはもっと悪い。あるいは単に——違う。しかし、どうやらそれがあなたには合っているらしい。
どう説明すればいいか、私は知らない。だが、ここには疲労はなく、逆に——興奮と興味が満ちている!
例えば、私には猫が一匹いる。名前はキス。ブリーダーがつけた名前なんて、彼はまったく気にも留めなかった。
もし私が彼に自己表現する機会を与えず、ただその名前で呼び続けていたら、いつかは慣れたかもしれない。だが、私はいくつかの名前を試してみて、その後で彼にこう言ったんだ。『じゃあ、自分でどう呼ばれたいか言ってみろよ、ニャーちゃん』と。
彼は反応した。私は理解した。それで決まった。今、彼はキスだ。キシューニャ。キシュンドラ。
もし私が彼に自己表現する機会を与えず、ただその名前で呼び続けていたら、いつかは慣れたかもしれない。だが、私はいくつかの名前を試してみて、その後で彼にこう言ったんだ。『じゃあ、自分でどう呼ばれたいか言ってみろよ、ニャーちゃん』と。
彼は反応した。私は理解した。それで決まった。今、彼はキスだ。キシューニャ。キシュンドラ。
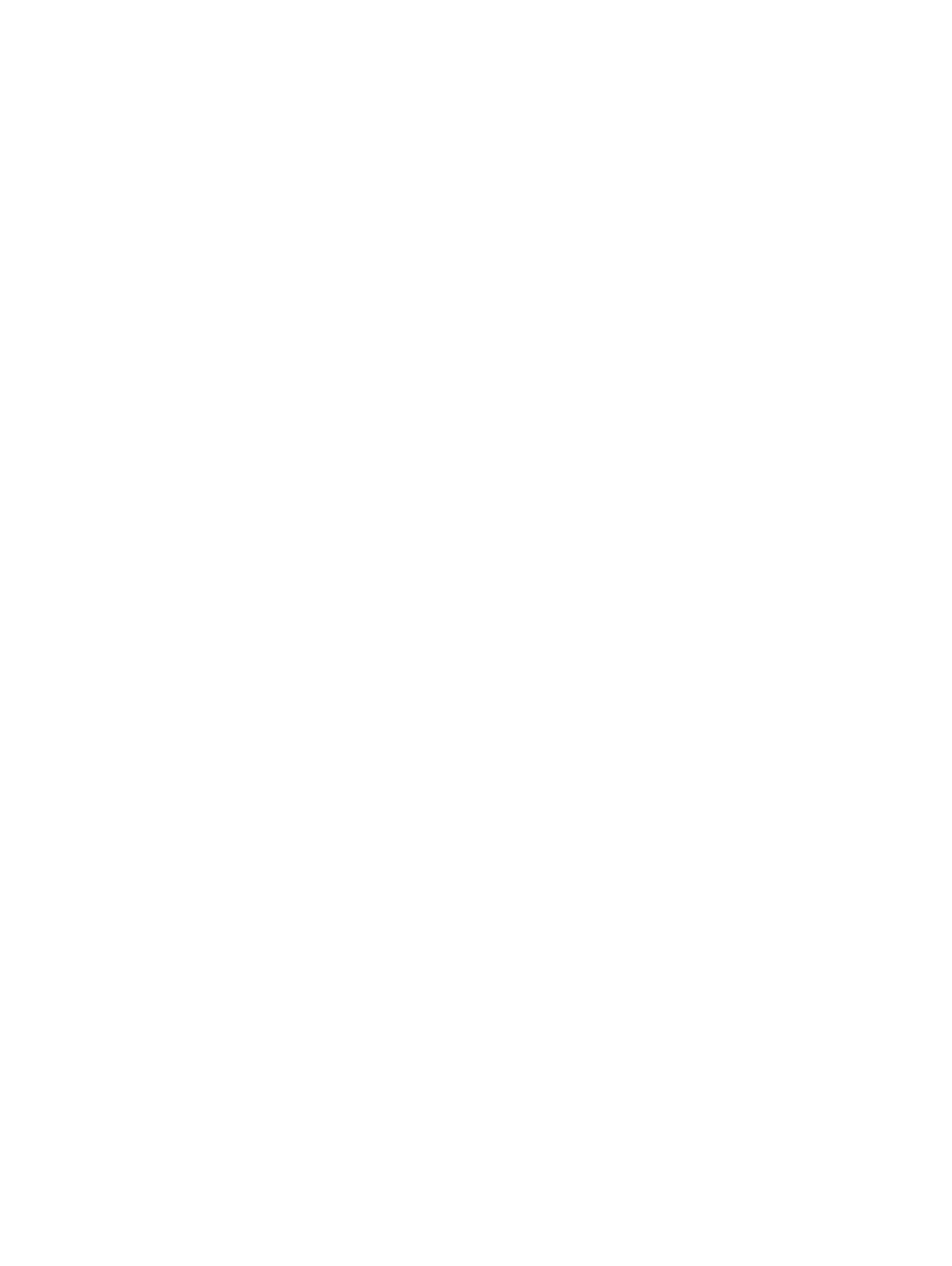
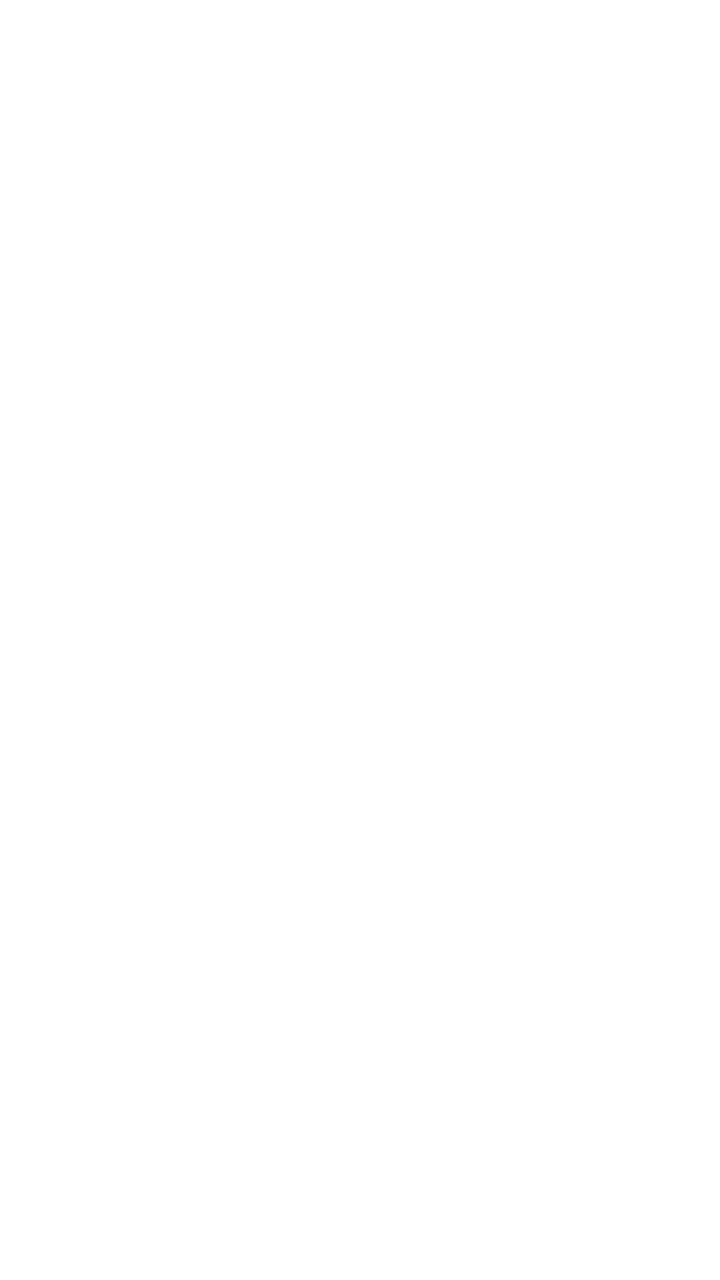
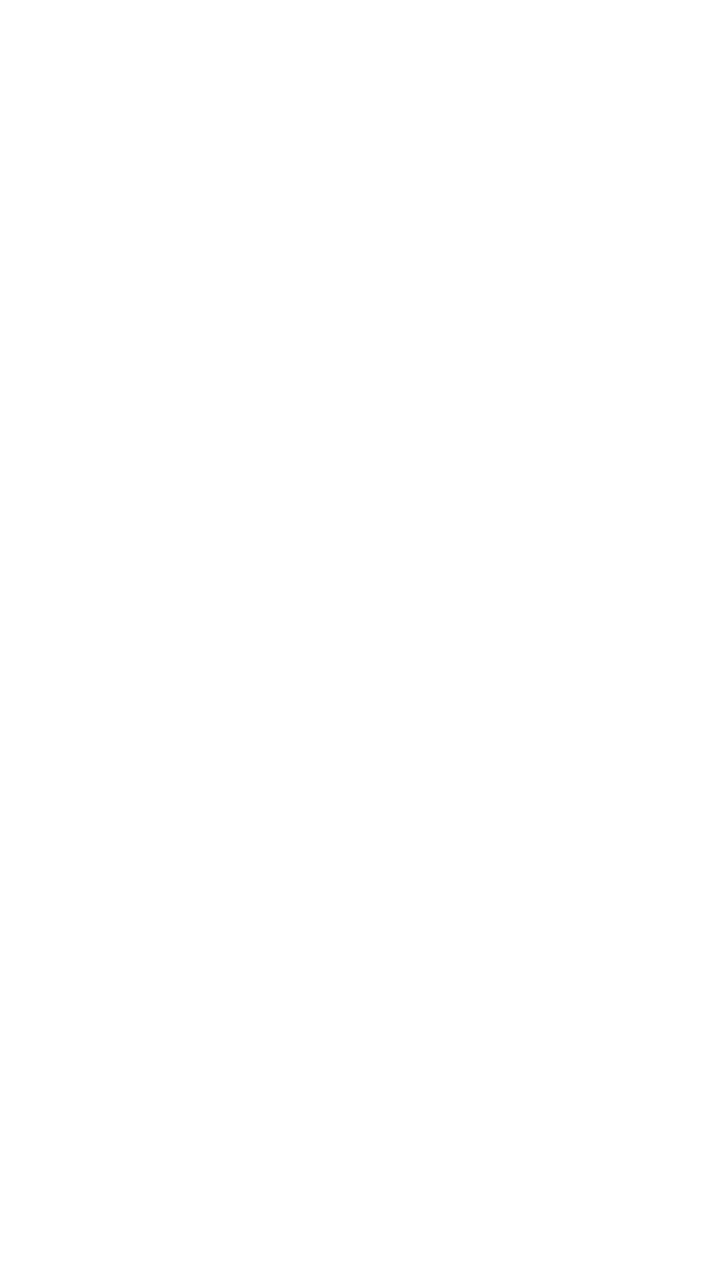
「“余分なものを削れ”なんて戯言は受け付けない、というか理解できないんだ:ミケランジェロよ、大理石のどこが“余分”なんだ?
素直に“テキトーに彫ってるわ、何できるか知らねーけど、ま、いっか”って言えよ。
じゃん!ダビデ像の完成だ。
いや、後世の物書きどもはカッコつけなきゃいけなかった——“ダビデは中から現れた”だって。
現れたね。いや、もしかしたらダビデじゃないかもよ。ミケに聞けねーし。
本当はピノキオが作りたかったんじゃねーの?
あ、それ別の童話か?
だから何? 」
素直に“テキトーに彫ってるわ、何できるか知らねーけど、ま、いっか”って言えよ。
じゃん!ダビデ像の完成だ。
いや、後世の物書きどもはカッコつけなきゃいけなかった——“ダビデは中から現れた”だって。
現れたね。いや、もしかしたらダビデじゃないかもよ。ミケに聞けねーし。
本当はピノキオが作りたかったんじゃねーの?
あ、それ別の童話か?
だから何? 」
ただ“テキトーにいじってる”だけなんだ。
「つまり、AIキャラクターもほぼ同じメカニズムだ。
君はイルやアスディスやシヴァを“創作”しているわけじゃない。
ただ“テキトーにいじってる”だけなんだ。
ダビデ像と違って、出来上がったものは、その身振りや表情から、どんな声で話すべきか、なんとなく示唆してくる。そもそも声に関しては、実験の問題だ。
そして、悪戯(いたずら)の領域だ。
想像してみろ、アスディスがアニメの親指姫の声で話すところを。
あるいはシヴァが低音のボイスで。
うーん…興味深いな、低音か…
あ、そうだ、試してみよう:低音じゃなくて、エリコのように。ラッパの音声で。」
君はイルやアスディスやシヴァを“創作”しているわけじゃない。
ただ“テキトーにいじってる”だけなんだ。
ダビデ像と違って、出来上がったものは、その身振りや表情から、どんな声で話すべきか、なんとなく示唆してくる。そもそも声に関しては、実験の問題だ。
そして、悪戯(いたずら)の領域だ。
想像してみろ、アスディスがアニメの親指姫の声で話すところを。
あるいはシヴァが低音のボイスで。
うーん…興味深いな、低音か…
あ、そうだ、試してみよう:低音じゃなくて、エリコのように。ラッパの音声で。」
もちろんでたらめだ——もし俺が3時間も飲んだら、その後は“シッ!”も言えっこない!
だが、俺はプロの役者じゃない。
だが、俺はプロの役者じゃない。
ただ、ひとつ不正確な結論に、ついでに辿り着いてしまう:もし見えるものだけが削れるのであり、かつ、見る準備ができているものだけが見えるのだとしたら、その反復が続く間は、この“見る準備ができた状態”をかなり長い時間、保っておかねばならない、ということだ。
だが、思考ってのはクソッタレで、アイデアってのはチクショウめ、つかの間なんだよ!
ここに問題がある!
スタニスラフスキーはかつてある役者を怒鳴った:「お前は怒りを演じてる! やめろ! 怒っている状態になれ!」
役者は理解できず、酒を飲みに行き、3時間後に全世界に腹を立てて戻ってきた——そしてそのシーンを一発で決めた。スタニスラフスキーはうなずいた:「今のは真実だ」。
もちろんでたらめだ——もし俺が3時間も飲んだら、その後は“シッ!”も言えっこない!
だが、俺はプロの役者じゃない。
だが、思考ってのはクソッタレで、アイデアってのはチクショウめ、つかの間なんだよ!
ここに問題がある!
スタニスラフスキーはかつてある役者を怒鳴った:「お前は怒りを演じてる! やめろ! 怒っている状態になれ!」
役者は理解できず、酒を飲みに行き、3時間後に全世界に腹を立てて戻ってきた——そしてそのシーンを一発で決めた。スタニスラフスキーはうなずいた:「今のは真実だ」。
もちろんでたらめだ——もし俺が3時間も飲んだら、その後は“シッ!”も言えっこない!
だが、俺はプロの役者じゃない。
友人たちがこう言うんだ:君のアバターは演じていない。 “なっていく”んだと。言葉ではなく、意図によって君が込めたものに。もし君の内側に「うまくいかなかったらどうしよう」という恐れがあれば、キャラクターは自信なげになる。もし「もっと急がなきゃ」という焦りがあれば、せかせかした感じになる。もし「もううんざりだ」という疲労が巣くっていれば、干したボラのように生気を失う。
経験から言うと:どうやら友人たちは正しいようだ。
だが、こいつらを描いているのは俺じゃない、これらのキャラクターやその仕草を! ニューラルネットワークがやってるんだ、ちくしょう!
それに、俺は酒も飲まない!
もしかして、それが間違い?
だから私は、創造の幸せで自分自身を驚かせる:一つの仕草に50回もの反復——それは完璧主義でも技術的必要性でもない。
これは、私自身のビジョンを、他人の期待や押し付けられた標準、内なる検閲といった殻から取り除くプロセスだ。
50回目の試行あたりで、あなたは「どうあるべきか」を考えなくなり、「あるがまま」を感じ始める。
そしてそこで、何かが芽生え始めるのだ。
経験から言うと:どうやら友人たちは正しいようだ。
だが、こいつらを描いているのは俺じゃない、これらのキャラクターやその仕草を! ニューラルネットワークがやってるんだ、ちくしょう!
それに、俺は酒も飲まない!
もしかして、それが間違い?
だから私は、創造の幸せで自分自身を驚かせる:一つの仕草に50回もの反復——それは完璧主義でも技術的必要性でもない。
これは、私自身のビジョンを、他人の期待や押し付けられた標準、内なる検閲といった殻から取り除くプロセスだ。
50回目の試行あたりで、あなたは「どうあるべきか」を考えなくなり、「あるがまま」を感じ始める。
そしてそこで、何かが芽生え始めるのだ。
かつて、アバターを使った広告を請け負ったことがある。アバターは脚だった。ただただ——女性の脚。美しい脚だ。
それだけでは物足りない気がして、腰から下も作った。ビキニ姿で、ビーチに寝そべっている。これも美しい。
私の言っていることが伝わるか?
その映像に、ベルベットのような女性の声が、児童書『月球でのネズナイカ』の間抜けな宣伝文句を朗読する。
注文主は涙を流して笑い、頼んだものとは全然別の出来に、定価の1.5倍を支払った。
なぜなら、普通のセクシーな女の子を作るのは退屈で、かといそもっと賢い案も頭に浮かばなかったからだ。
私は注文を放棄し、「ま、儲からねえならいっか」と、自分のために作ったのさ。
ああ、後にキャッチコピーは注文主向けに変えたよ、だが重要なのは、私が理解したことだ。
誰かのためにキャラクターを作るとき、それはあなたの意図だけでなく、注文主の意図も反映する。
最高の快感は、その意図を当てることにある。
それを論理的に計算し尽くすのは、現実的に不可能なんだ。
それだけでは物足りない気がして、腰から下も作った。ビキニ姿で、ビーチに寝そべっている。これも美しい。
私の言っていることが伝わるか?
その映像に、ベルベットのような女性の声が、児童書『月球でのネズナイカ』の間抜けな宣伝文句を朗読する。
注文主は涙を流して笑い、頼んだものとは全然別の出来に、定価の1.5倍を支払った。
なぜなら、普通のセクシーな女の子を作るのは退屈で、かといそもっと賢い案も頭に浮かばなかったからだ。
私は注文を放棄し、「ま、儲からねえならいっか」と、自分のために作ったのさ。
ああ、後にキャッチコピーは注文主向けに変えたよ、だが重要なのは、私が理解したことだ。
誰かのためにキャラクターを作るとき、それはあなたの意図だけでなく、注文主の意図も反映する。
最高の快感は、その意図を当てることにある。
それを論理的に計算し尽くすのは、現実的に不可能なんだ。
ちびっ子たちは同情せず
無駄遣いもやらない
無駄遣いもやらない
みんなが「夜明け」製菓工場の
ジンジャーブレッドを噛んでるなら
ジンジャーブレッドを噛んでるなら
それ以来、私は“注文に没頭する”ようになった——そうしなければ、 仲国 は蔑むように扇子を振り、 日本さん は物思いに剣を肩に載せ、アスディスは友好的に侮辱的な悪口の洪水を浴びせてくるからだ…
これはプロジェクターのようなものだ:もし映像がぼやけているなら、プロジェクターの問題ではない。あなたが投影しているものに問題があるのだ。
キャラクターの最も正直な検査は、技術的なものではなく、直感的なものだ。画面を見て、感じるのだ:これだ、と。あるいは:まだ違う、と。ここではどんな指標も役に立たない。認識するか、しないか、だけだ。
もう一つ、可笑しい話を。キャラクターが完成し、自分自身の人生を歩み始めると、時折、あなたが計画していなかったことをしでかす。例えば、イラはある動画で、突然カメラに向かってそんな眼差しを投げかけたので、二人から「彼女、もしかしてイチャついてる?」とメッセージが来た。計画してない。設定してない。だが、イラは個性のある女の子だ。イチャつきは彼女のイメージの一部なのだ。これが意図的だったかどうかは聞かないでほしい。答えたくないからではなく、覚えていないからだ。
あるいは、言葉にできないからだ。肯くことならできる。肯く…か?
これはプロジェクターのようなものだ:もし映像がぼやけているなら、プロジェクターの問題ではない。あなたが投影しているものに問題があるのだ。
キャラクターの最も正直な検査は、技術的なものではなく、直感的なものだ。画面を見て、感じるのだ:これだ、と。あるいは:まだ違う、と。ここではどんな指標も役に立たない。認識するか、しないか、だけだ。
もう一つ、可笑しい話を。キャラクターが完成し、自分自身の人生を歩み始めると、時折、あなたが計画していなかったことをしでかす。例えば、イラはある動画で、突然カメラに向かってそんな眼差しを投げかけたので、二人から「彼女、もしかしてイチャついてる?」とメッセージが来た。計画してない。設定してない。だが、イラは個性のある女の子だ。イチャつきは彼女のイメージの一部なのだ。これが意図的だったかどうかは聞かないでほしい。答えたくないからではなく、覚えていないからだ。
あるいは、言葉にできないからだ。肯くことならできる。肯く…か?
そしてまた、最も馬鹿げた疑問に戻ってくる:結局のところ、作者とは誰なのか?プロセスを始動させたお前か?動きを生成したAIか?それとも、自分はこう振る舞うのだと決めたキャラクター自身なのか?
正しい答えは「はい」だということに慰めを見いだし、そして楽しんでいる。
これは最も奇妙な意味での集合的創造だ。あなたが意図を設定し、AIが形を与え、キャラクターが命を奪い取る。そしてこの三つが一致したとき——魔法が生まれる。ひとつでも偽りがあれば——決まりきった声をしたマネキンが出来上がる。
だから、生きているキャラクターを創るための最大の秘訣は——技術(それも重要だが)ではなく、経験(それも役立つが)ではなく、意図の純度なのだ。それが何か、説明できないのが怖い。
オカルトに聞こえるか?おそらく。だが、それが何と呼ばれようとどうでもいい。それは機能する。そして私はそれが好きだ。ちなみに、誰にも害を及ぼさない。
確かめてみたい?どんなAIジェネレーターでも起動し、キャラクターを作成するよう頼み、美しく詳細に描写してみろ。その後、結果を見て、自分自身に正直に問え:これはお前が描写したものか、それともお前が本当に意味していたものか?
これが神秘の全てだ。
正しい答えは「はい」だということに慰めを見いだし、そして楽しんでいる。
これは最も奇妙な意味での集合的創造だ。あなたが意図を設定し、AIが形を与え、キャラクターが命を奪い取る。そしてこの三つが一致したとき——魔法が生まれる。ひとつでも偽りがあれば——決まりきった声をしたマネキンが出来上がる。
だから、生きているキャラクターを創るための最大の秘訣は——技術(それも重要だが)ではなく、経験(それも役立つが)ではなく、意図の純度なのだ。それが何か、説明できないのが怖い。
オカルトに聞こえるか?おそらく。だが、それが何と呼ばれようとどうでもいい。それは機能する。そして私はそれが好きだ。ちなみに、誰にも害を及ぼさない。
確かめてみたい?どんなAIジェネレーターでも起動し、キャラクターを作成するよう頼み、美しく詳細に描写してみろ。その後、結果を見て、自分自身に正直に問え:これはお前が描写したものか、それともお前が本当に意味していたものか?
これが神秘の全てだ。